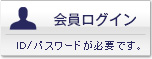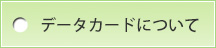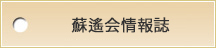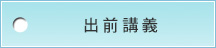●場 所 : 博多サンヒルズホテル(福岡市博多区吉塚本町13-55)
●出席者 : 62名(大学からの来賓4名含む)
熊本大学工業会福岡支部土木部会では、令和6年度総会を開催し、来賓として工業会会長の山尾先生、工学部土木建築学科助教の渡部先生、蘇遙会学生部長の仁戸田様、副部長の須藤様にご出席いただきました。
総会は、右田会長(S59卒)の挨拶に続き、来賓挨拶として、山尾先生と渡部先生から最近の大学の動向や同窓生のつながりの大切さなど、貴重なお話をいただきました。
懇親会は、城様(S41卒)の乾杯ご発声により開宴となり、大学、民間、行政の意見交換や若手と先輩の交流など、大盛況のうちにあっという間に2時間余りが過ぎました。
最後は、出席者全員で肩を組んで、学生の仁戸田様による初披露の巻頭言で五校寮歌「血をすすり涙して」を合唱し、一致団結した締めくくりとなりました。
これからも、同窓生の皆さんが旧交を温め、貴重な交流の場となるよう、総会を盛り上げていきたいと考えています。
また、今回参加できなかった同窓生の皆さんにも、来年の総会でお会いできることを願っております。
※令和7年度総会(予定)
日 時 : 令和7年11月6日(木)18時~
場 所 : 博多サンヒルズホテル(福岡市博多区吉塚本町13-55)
(幹事:大石H6卒)
%E8%98%87%E9%81%99%E4%BC%9A%E6%83%85%E5%A0%B1%E8%AA%8C_%E5%8E%9F%E7%A8%BF0819_0001_0001.gif)